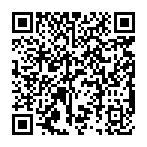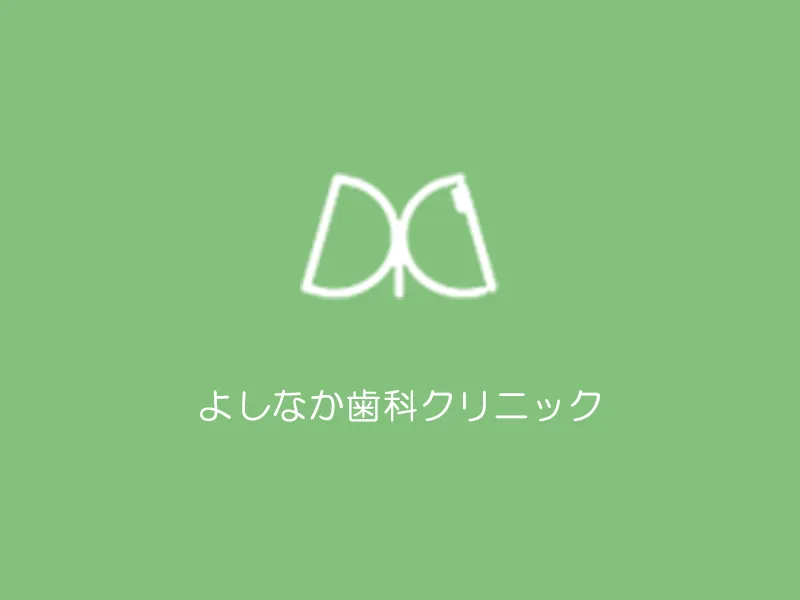ブログ
2015/03/12
ブログ
入れ歯について知ろう−その25−入れ歯の歯肉の形で入れ歯の安定さが変わる!
アンケートありがとうございました。
新たにページを作成し、まとめました。ご協力ありがとうございました。
定期的に行いたいと思いますのでご協力よろしくお願い致します。
歯肉形成、つまり入れ歯の歯ぐきのお話です。
前々日は審美、前日は発音についてお話ししました。
義歯(入れ歯)の形を見て、辺縁と呼ばれる、簡単に言えば、表(研磨面)と裏(粘膜面)の境目の部分の形が
義歯の安定を決定づける重要な要素である、というお話です。
義歯の辺縁は少し膨れた形になっているのが理想とされています。
この形をコルベン状というのですが、
コルベンって何?というとコルベンはこん棒のことです。
こん棒といってもこれもピンと来ないと思うのですが、
古代人が狩りをするときに使っていた木の棒、ちょうどバットを太くしたような感じでしょうか。
話が逸れましたが、この辺縁部分を膨らませることで義歯がしっかりと落ち着くことになります。
義歯は頬と舌に囲まれた部分にあるのですが、噛むなどのその他の行為でそれぞれから力を受けます。
これをコルベン状、すなわち辺縁部を太らせることで口腔内では次のような力が働きます。

頬と舌の力が入れ歯を離脱と逆の力へを変換することができます。
しかし、この形が不十分であった場合、どのようなことが起こるかというと

頬、舌の力が義歯を離脱される力に変換されることになります。
入れ歯の赤い部分、歯肉の部分は審美だけでなく、このように義歯の
安定にとても重要であるということになります。
しかし、状況によっては、このようなコルベン状を作ることができない場合も
あります。
この形をどのように作ればいいのでしょうか。
どうしても難しい場合は、頬、舌それぞれの力を記録することを行います。
特殊な方法ですが、次回少し紹介をします。
RECOMMEND
関連記事