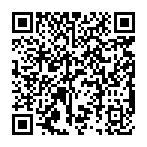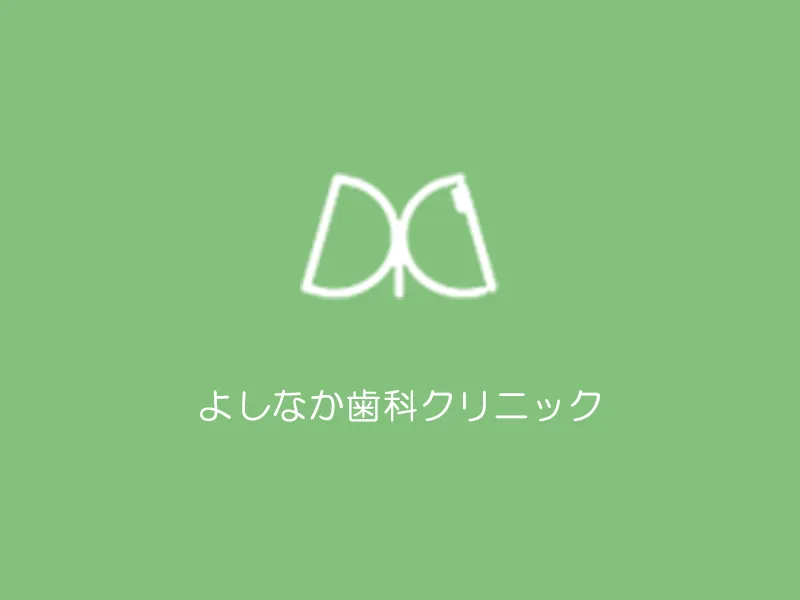ブログ
2015/02/16
ブログ
入れ歯について知ろう−その5−歯を失うと顎の大きさが変わる
受験にもよく使われるメモリーツリー。
娘が地理を勉強していますが、理科と絡めた勉強でなぜ、そうなるのかというのを覚えるのではなくて
理解する、ということが大事だなとさいきんつくづく思います。
扇状地、という地形ですが、字の通り、扇型に拡がった地形です。
水の流れでできるものですが、
理科で早い流れは大きな石を運ぶが、緩い流れは石が流れず堆積する
という原理から扇状地ができているということを理解するべきだと思います。
山間の急流は山を削っていきますが、山を抜けると流れは緩やかになります。
すると削られた土砂は積もっていきます。
水は行き場を失って横に拡がって結果扇形の堆積地ができる
それが扇状地です。
単純に扇状地を覚えても面白くないから、その背景も知るほうが楽しいよ
ということを言いましたが理解してくれているでしょうか。。。
閑話休題。
歯が失われると上顎、下顎それぞれ固有の現象が起こるというお話をします。
その前に歯列、という言葉があります。歯の並びを指す言葉ですが、

この歯列は弓のように並んでいるため、歯列弓と呼びます。
そして、歯を失ったときに歯ぐきの土手の頂上をつないだものを顎堤弓と呼びます。
結論から言うと、歯を失ったら
上顎はこの弓が狭くなる
下顎は弓が広くなる
傾向があります。
_
実は上顎と下顎の骨は厚みと性状が違います。上顎は頭がい骨と同じ性状の骨でやや脆弱で、かつ頬側(外側)の骨が薄く、口蓋側(内側)の骨が厚い
ので、歯を失うと外側の骨が吸収されやすく、結果弓が狭くなることになります。
一方、下顎は体幹骨と同じ性状の骨なので丈夫で、かつ頬側(外側)の骨が厚く、舌側(内側)の骨が薄い
ので、歯を失うと内側の骨が吸収されやすく、結果弓が広くなることになります。
よく歯があるときを思い出して下さい。
歯があるときは上の歯が外側に出ているのに対し
歯を失った後の顎堤頂の関係は逆転してしまうことが多くあります。
これが歯を失ったときの上顎、下顎の特徴的な変化です。
噛み合わせを作るときにこの状態でどのようにバランスを作っていくか、それを
解決するもっともスタンダードな方法が、“歯槽頂間線の法則”と呼ばれる解決法です。
これについては明日にお話します。
RECOMMEND
関連記事