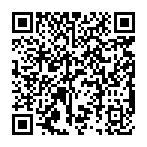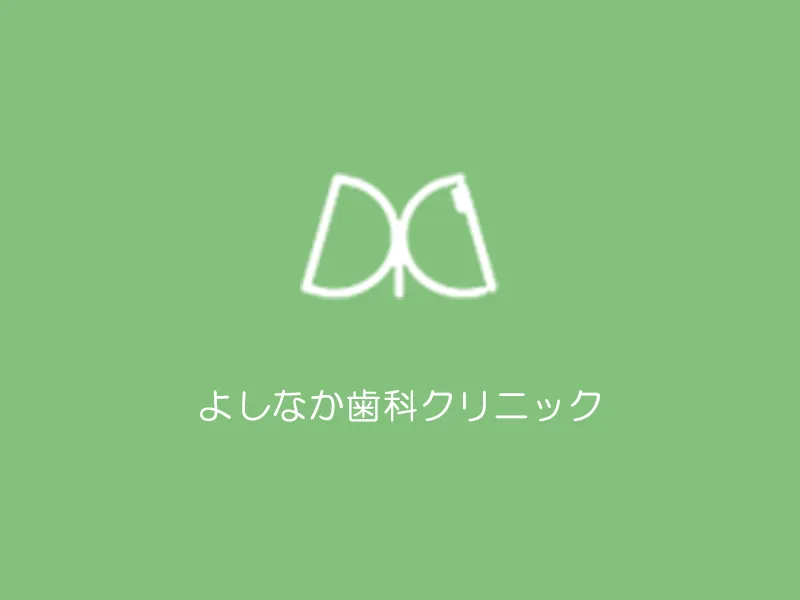ブログ
2014/12/19
ブログ
管楽器や口笛とお口の関係
私たちが何気なくしている口笛や管楽器演奏(特定の人しかしませんが、リコーダーならば全員は通っている道ですね)は口の中のいろいろな機能が連携してこその奇跡であるということを覚えて頂ければと思います。
口笛も管楽器も、特定のマウスピースや隙間に息のスピード、量、角度をコントロールして呼気をあてることで音がでます。
口笛では隙間は上下の唇が微妙な間隔、舌の三次元的な配置により、マウスピースをくわえた場合では、マウスピースを加える口および周囲の筋肉の適度な緊張により固有環境を作り出します。
口腔周囲の筋肉は口角挙筋、口角下制筋など、十二対もの筋がひしめきあっています。
少し奥に行くと、咽頭があります。ここは鼻と口を閉鎖する部分、軟口蓋と咽頭後壁があります。
この閉鎖機能が不十分な場合は口腔内圧が十分に上がらず、鼻に息が漏れてしまったります。
この閉鎖を行う筋は口蓋帆挙筋、上咽頭収縮筋が関与します。
さらに奥へ行くと喉頭があります。喉頭を自由に動かせるようになる(訓練でできるようになります)と喉頭部分の気道を拡げて多くの呼気を排出できるようになるそうです。(このあたりは感覚的なものなので証明が難しいのですが)
一定の呼気の圧・量が保てないと、音が揺れてしまうので、これらをコントロールする訓練がよく見かけるロングトーンですね。
で、よく考えて頂きたいのですが、筋肉を酷使すると、疲労をしますが、楽器を吹いている人は、長時間行っている人が多いです。使用する筋肉が疲労に強いというのも実は特徴であったりします。
しかし、顔面神経麻痺や、先天的、あるいは後天的な機能障害になってしまうと
口笛や管楽器演奏はおろか、通常の会話も難しくなってしまうことすらあります。
何気ない動作も細かく見ていくと面白いですよ。
RECOMMEND
関連記事